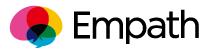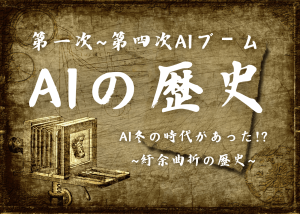【ウェビナーレポート vol.1前編】「条例化が進むカスハラ対策 コールセンターの現場で取り組むべき施策とDXについて」
「条例化が進むカスハラ対策 コールセンターの現場で取り組むべき施策とDXについて」
記事前編「カスハラに係る法整備化の現状と現場対応での課題」

導入
顧客が企業に対して理不尽なクレームや要求等を行う「カスタマーハラスメント」が、注目を集めて久しい。その間、対応する側も決して手をこまねいていたわけではない。毅然とした対応を取るという方針を打ち出し、続々と対策に乗り出す企業。行政サイドでも厚生労働省が2022年にカスハラに係る対策マニュアルを作成し、東京都をはじめとした複数の自治体が条例化を打ち出すなど、顧客の暴走に歯止めをかける動きが急ピッチで進められている。
では、常に最前線で顧客の苦情への対応に追われるコールセンターは、どのような状況に置かれ、対策が講じられているのか?
昨年10月(12月にアーカイブ配信)、『コールセンターDX 現場で本当に必要なDXとは』と題するオンラインカンファレンスを開催。コールセンター事情に精通する株式会社リックテレコム取締役・矢島竜児氏にご登壇いただき、カスハラに係る法整備化の現状と現場対応での課題について詳しくお伺いした。この記事ではセッション内容を詳しくご紹介する。
○対談者プロフィール
矢島竜児
株式会社リックテレコム 取締役、月刊「コールセンタージャパン」編集部・編集長
1998年リックテレコム入社。以降、センター運営企業などへの取材活動及び調査に従事。「コールセンター白書」の発刊、コールセンター専用Webサイトの運営、日本最大級のコンファレンス「コールセンター/CRMデモ&コンファレンス」の運営・企画等を手がけ、「コールセンター・アワード」の審査員を務める。
下地貴明
株式会社シーエーシー 新規事業開発本部 感情解析推進室室長
感情解析のAI開発に携わり、コールセンター現場での活用を目指す。
カスハラに対する法整備化の現状について
下地:本日はリックテレコムの矢島さんをお迎えして、「条例化が進むカスハラ対策 コールセンターの現場で取り組むべき施策とDXについて」をテーマに、まさに今法整備化が進んでいるカスハラ対策について、コンタクトセンターでどのような取り組みをすべきかを中心にお話を伺います。
では早速、カスハラに係る法整備化が今自治体を中心に進められていると思いますが、実際いつ頃、どのレベルで法整備化されていくのか、ご存じのことがあれば、教えていただけますか?
矢島:一般的に報道されていることしか分かりませんが、東京都をはじめいくつかの自治体で条例化することを打ち出しています(2025年4月に施行予定)。少しずつ他の自治体にも波及しています。実際に条例がつくられるかはともかく、2025年中に多くの自治体で、条例化の方向性だけはきちんとなるのではないかと期待されます。ただ、どの条例や規制についても大体は同様で、罰則の有無が結構曖昧になるというか、あまり具体的な罰則を盛り込まないものが、こういったケースでは多いです。そこの温度感が自治体で差が出るのか、それとも一番早いと思われる東京都に横並びになるのかが注目です。店舗などのリアルの顧客接点の場合、例えば手を出せば即座に犯罪ですし、分かりやすい。しかし、コールセンターの場合は声だけなので、判断が難しくなる局面もあるのではと想像します。
下地:確かに新聞各紙では、東京都は罰則の規定をつくらないと言われています。一方で対象となるのが、電話をかけてきた顧客側なのか、事業者側にも責任があるのかというので、様々な憶測が飛び交っていると思います。この辺りはどうなっていくイメージですか?
矢島:事業者側への規制は、一定レベルであるとは思います。ただ、罰則が伴うほどの厳しくなる印象は、現在のところ私はもっていません。報道やいろんな話を聞くと、一般消費者のエスカレートするカスハラに、どうブレーキをかけるかに主眼が置かれています。企業側では、2022年に出された厚労省のガイドラインをベースにきちんと体制をつくっていくことが、努力義務という形で動いています。そこが今後どう強化されていくのか、というほうが事業者側にとってはポイントになるでしょう。あとは管轄団体です。コールセンターの場合は、日本コンタクトセンター協会があるのですが、どちらかと言うと、例えば金融や電気、百貨店など、各業界団体が対応方針についてのガイドライン的なものを示すかどうかに注目したいです。
事業者側がカスハラを防ぐのは極めて困難
下地:私も基本的には顧客側に対して事業者が自社の働く人たちを守っていくスタンスで行われていくと見ていました。一方で『コールセンタージャパン』の昨年11月の記事で、カスハラ対応を行うセンターはどれくらいあるかという質問に、約67%がまだルールを決められていないとの回答でした。こういった事業者側でどのような準備をしていくと、カスハラを防いでいけるのかを、ぜひお伺いしたいです。
矢島:カスハラを事業者側が主導して防ぐのは、かなり難しいと思います。毅然とした対応を取る、というのは任天堂さんが皮切りになり、JR等いろんな会社が同様に打ち出し、公言しています。これが1つの抑止効果になればいいのですが、私の印象では、なかなか難しいと思っています。特に電話対応に関しては、リアルな接点よりも、企業側のアプローチで防止するのは難易度が上がるのではないでしょうか。発生した時にどうするかという対症療法に近くなってしまうので、「そういう時にどうするのか」「毅然とした対応とは何なのか」を明示する必要があります。毅然とした対応と言っても、具体的にどのような対応なのかが、実はよく分かりません。その点に関しては、現段階でこうする、こうすべきというのは言いにくいと思いますが、「切電」のルール化はひとつの手段だと思います。
受け手側の感覚の違いが、定義づけを難しくする
下地:なるほど。お客様を選べないと言うと、言い方がよくないかもしれませんが、どうしても一定数出てしまうと思います。毅然とした対応を取るところでよく言われるのが、「クレームは甘んじて受けて、改善に繋げていくべきだ」との話がある一方で、「カスハラは全く別物と区別をして考えるべきだ」という声もあります。この辺り、カスハラとクレームの差について、センターの中ではどう理解していくべきなのでしょうか?
矢島:いま、企業が注目しているのは、AIによる取り組みです。ただ、ITツールの使用や、教育・人材育成を行う前に「カスハラの定義」が絶対に必要なはずです。「これはカスハラで、ここまではご指摘」という定義をなるべく明示する。グレーゾーンはどうしても発生するものの、それをどこまで狭くできるかが、大きなポイントになるでしょう。きちんと定義づけしないと、ハラスメントという言葉が企業側、現場の「錦の御旗」に使われてしまうのを、非常に危惧しています。受け手側であるオペレーターが、ハラスメントと言ってしまえば、すべてそうなってしまう。言っている内容は至極もっともなご指摘だけれども、口調が少しきついなど、かなりありがちです。「これってどうなの?」という線引きがすごく難しい。これをマネジメント側がなるべくはっきりと示す努力をしないと、何をやったところで、全部対症療法で終わってしまう。すべてはここだと思っています。
下地:オペレーターが「嫌だな」と思った瞬間に、働くことを拒否し始めていくと、元々のセンターの意義である、困っているお客様に対しての対応ができなくなってしまいます。そこは本末転倒だと?
矢島:そうですね。それもあります。要は「嫌だな」とハラスメントに感じる温度が、オペレーターごとに違うはずです。俗な表現をすると、打たれ強い人もいれば、すぐにへこんでしまう人もいる。これを同じ基準にどこまで揃えられるかが、カスハラの定義づけの部分では、一番、難しいと思います。オペレーターを守る姿勢は当然、必要です。そこを一番傷つきやすいと言うと少し語弊があるかもしれませんが、そこのラインに合わせてしまうと、今度はまっとうなご指摘が企業側に入らなくなる。セクハラは論外ですが、パワハラなどでも言えることで、どうしてもハラスメントという言葉は錦の御旗に使われやすい。ハラスメント・ハラスメントという言葉がもう出ているくらいです。「それって本当にカスハラなの?」という視点もどこかで必要になってくるのではないでしょうか。
カスハラの対応には「定義づけ」が必須
下地:一方でカスハラがここまで言われて、仮に「従業員に対して何らかの侵害を与える行為をした瞬間にカスハラ」だと定義を立てたとして、顧客側に「あなたは今カスハラをしている最中です」と、どう伝えるのか。オフラインでは、責任者が出て来て、話したりして何となく状況が変わったと分かります。その点、電話中は1対1の密室でのコミュニケーションの状態です。オペレーターを守る意味でも、どう伝えていくといいのでしょうか?
矢島:まずは組織対応のルールを決めないといけないと思います。カスハラに限らず、重クレームも同様ですが、オペレーター個々人に任せるやり方が一番のNG。組織として対応する、要はエスカレーションルールを定義に基づいて決めていくという順序が必要です。
お客様に「あなたが言っていることは暴言や誹謗中傷であって、これ以上ご対応できません」と伝える役割をオペレーターに担わせるケース、エスカレーションされた責任者、リーダークラスの方が対応されるケース、もう1つは、私は某社のデモンストレーションで見ただけですが、それを機械(あるいは録音)音声にやらせる方法。一定の閾値になるキーワードを予め設定しておく、もしくは、それをオペレーター側でコントロールでき、話している最中にオペレーターではなくて、機械音声などで「それ以上続けられると、電話を切らせていただきます」などの音声を流すやり方も、すでにあります。ただどちらにしろ、「これをやってはダメ(カスハラ)」という定義がまず必要です。
下地:確かにそうですね。定義もないまま人が変わっていったり、AIが急に出てきたりすると、「何のことだ」という感じになってしまいます。
矢島:判断基準がばらつくと企業が信頼を失うので、何よりもまずは定義をきちんとすることがポイントになると思います。
休憩と声掛けで共感を示すのが、オペレーターケアのセオリー
下地:では、カスハラが起きてしまってしんどい目にあったオペレーターのケアの観点で言うと、何か気をつけられているセンターはありますか?
矢島:マメな声掛けと、ヘビーな対応をした場合はその直後に休憩を与えるやり方がセオリーです。すぐに次のコールを受けるのは、しんどいですよね。休憩を与える、リーダーの声掛けといった共感を示してあげるのが、一番大きなポイントになると思います。
オペレーター任せではなく、組織で対応する
下地:いくつか紙面を見ていて、いいなと思ったのが、必ず1対1にしないというか。ヘビーなカスハラになってくると、SV(スーパーバイザー)が必ず隣にいて、フォローすると。組織は見放していないとメッセージを与えるのも、すごく効果的だと感じました。
矢島:やはり、オペレーターだけに任せてはダメだと思います。組織対応という部分がポイントです。組織として対応しているのであって、あなたのせいではないですよという姿勢を示さないといけません。もちろん、オペレーターの対応がもとでこじれることはあります。しかし、カスハラ、クレームの大元の原因はオペレーターにないケースも多いです。根源は別にあって、ただ電話をかけて対応したオペレーターの態度があまりよくないので、こじれるケースはあります。
下地:顧客体験として、製品が悪いというところでやった上に、応対が悪かったので、火がついてしまうということですね。
矢島:それはもうカスハラというより、正当なご指摘として受けなければいけない案件です。ただ、そこで相手側の口調や表現があまりにもひどいとなったら、カスハラの案件になります。受け手側の感覚の温度差が出てくるので、この判断と対処が一番難しいです。繰り返しになりますが、きちんと定義をつけられるかがやはりポイントです。
下地:そうですね。例えば関東の方が、大阪の南のほうのすごい関西弁でまくし立てられると、やはり怖いというのがありますから。
矢島:僕は九州出身ですが、少し威圧感を感じる方言があったりするのでわかります。でも、それは基準としては、無視しないといけないと思います。
まとめ・次回予告
以上のようにオンラインカンファレンスの前半では、カスハラの法整備化の現状及びコールセンターでの対応における課題について議論が行われた。法整備は、主要な都市から進められていくとみられるが、罰則の有無等が自治体間で差が出るか否かが注目される。現場対応においては、対応やその基準づくりにおいて、不可欠なものは「定義づけ」であることを矢島氏は強調した。一方でカスハラと感じる度合いに個人差があることが、定義づけを難しくしている要因だとも指摘。今後の対応を注視していく必要があるだろう。
続く記事では、後半に議論された内容を取り上げる。現状AIやITといったテクノロジーがどの程度コールセンターに活用されているのか、またその上での課題や今後の展望についても専門家の視点を交えながら言及されている。カスハラに対処するための新たな現場対応の在り方や最新技術の活用方法について考えていただく一助として、あわせてお読みいただければ幸いである。
Empathの詳細についてはこちらから↓
音声感情解析AI Empath (webempath.com)
Beluga Box SaaS(コールセンター向け製品)の詳細についてはこちらから↓
https://belugabox.webempath.ai/
DMでも情報発信しております。
DMの配信登録はこちらから
この記事に関するお問い合わせはこちら
株式会社シーエーシー
Empath事業推進室
empath_info@cac.co.jp